標語の裏に潜む嘘

世に蔓延っている「モットー」や「スローガン」と呼ばれる標語は、時として大勢を動かす原動力となるが、反対に誰もが一斉に首を傾げ、追従しないようなものにもなりうる。
後者の状態に陥りやすいケースは想像に難くないだろう。有言不実行のように、言動と行動との間に齟齬が発生すれば、掲げた標語はたちまち大言壮語となり果ててしまう。もちろんこれは、口頭で伝えた際にも起こり得る現象である。さて、今回は黒歴史から少し離れ、大言壮語を通り越しもはや虚言となり下がった標語が、私にどのような影響をもたらしたかを記していこう。
中学生ともなると、私のクラスメート達は続々と塾に通い始めた。この頃の私はと言えば、ただでさえ学校から出される宿題に四苦八苦しているというのに物好きな奴らだ、とわざわざ塾に通う彼らを奇異の目で見ていた。
だがその内そんなことも言えなくなるほど英語以外の勉強の習慣が疎かになっていったため、先述の彼らと同様、塾に通い始める。
塾に通い始める前、そして通っている最中も、その塾の室長にまるで呪文のように唱えられていた言葉がある。それは「僕らはいつでも君の味方。分からないことは何でも先生に聞いて。」という言葉である。月並みだけれど頼りがいのある文字の羅列-軽い反抗期を迎え孤軍奮闘を軸に据え始めた私にとっては、まるで百戦錬磨の味方が側近となったように感じられた。
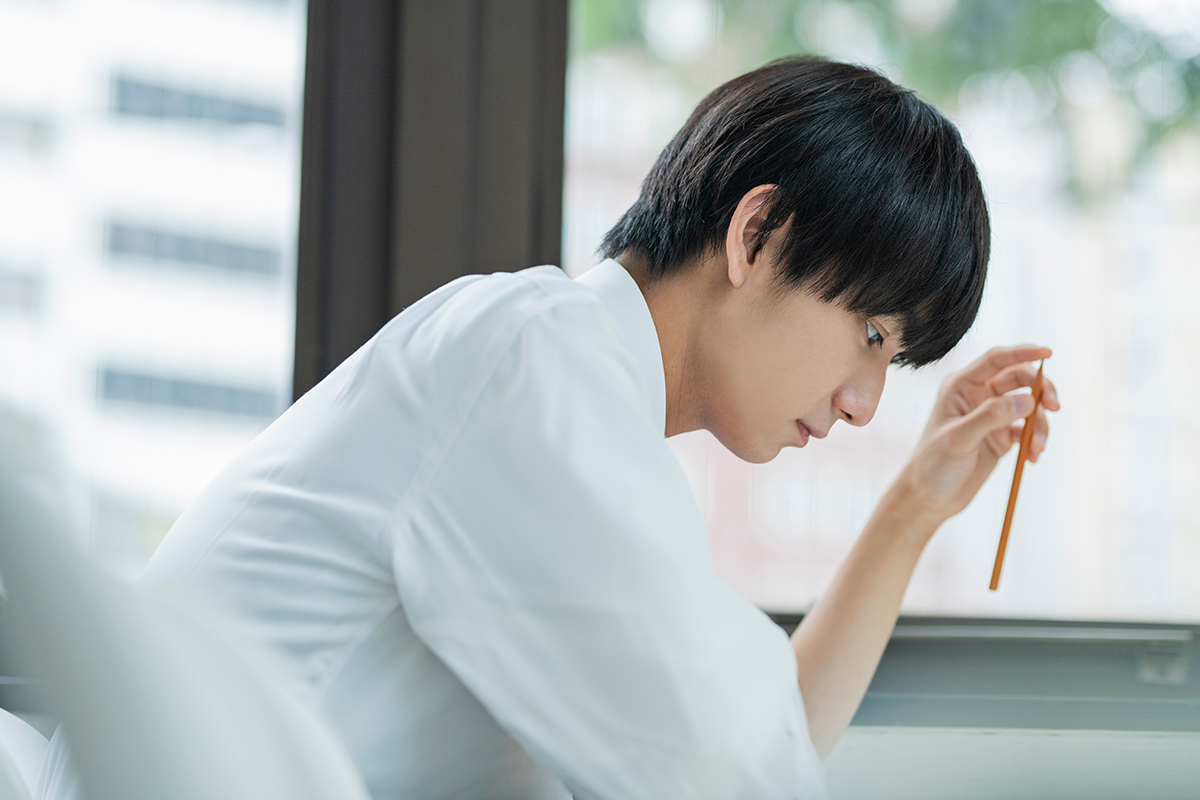
さて、塾に通った経験のある読者の方々もいると思うが少し解説を入れておこう。塾というのは大きく分けて二種類あり、一つ目が集団塾、二つ目が個別指導塾である。前者は学校の授業さながらの形式、後者は家庭教師のように、生徒本人のスタイルに合わせた授業する形式である。当時の私は自他ともに認めるほど我が強かったため、個別指導塾に通塾していた。
個別指導塾では基本的に相性の合う講師を選び、その人に授業をしてもらうことになるが、先述した通り、あの頃の私は本当に面倒くさい人間であったため、その「相性の合う講師」探しは難航していた。そんな私のもとに、塾の定期面談の話が舞い込んできた。
面談内容は非常に単純なもので「相性の合う講師はいたか」というものであった。当時私が通っていた塾では担任制のようなものを取り入れており、生徒一人に担当講師を一人付けるスタイルで授業をしていた。簡単に言ってしまえば、ホストやキャバクラでよく耳にする本指名の感覚に近いだろうか。
その面談が行われる前、私は三人の講師に授業をしてもらっていた。何もその中から必ず一人選ばなくてはいけない訳ではない(もう少し色々な講師を見てみたい、とでも言えばこの場はしのげる)が、その時の私にそんな策は練れず、それどころか「三人の中から選ぶとかポケモンじゃん。」と、ヒトカゲ、ゼニガメ、フシギダネの中から選ぶ新米トレーナーと自分を重ねてしまったため、結果初期の三人の中から一人選ぶことになった。
さて、パートナー(当時本当にそっくりであったため、以降フシギダネと表記する)を選択し終えた私は二人三脚でフシギダネと歩んでいることになるのだが、ここで当時の私の性格の最悪の部分が露呈することになる。
そう、信じられないほど飽き性だったのだ。
走ることは好きだったが景色の変わらないルームランナーは極端に苦手であった私にとって、講師が全く変わらないというシステムは非常に相性が悪かったのである。
それこそ初めの内は「この人と一緒に頑張るぞ。」と思っていたのだが、だんだんと私の中で、景色が変わらない、という感覚が芽生え始めてきた。このままでは自分の飽き性のせいで他人に迷惑がかかってしまう-そう思った私は少しでも見える景色を変えようと趣向を凝らした利用方法を思いついた。それは、予習をしてその内容をフシギダネに質問するという、優等生なら誰でも思いつくものであった。
思い立ったが吉日、私はすぐに行動に起こした。自習スペースのような場所を借り、そこで数学の予習に取り掛かった。
ここで私の以前のエッセイを読了した読者なら、ここからの惨劇を察することが出来るだろう。そう、私の矮小な数学力では予習内容を全く理解出来なかったのだ。とどのつまり、企画倒れである。
しかしそこで私は代替案を思いついた。「それなら質問しに行けばいいじゃない。」と。
その妙案が生み出される過程の中に一つの言葉があった。それはこの塾の魔法の言葉「僕らはいつでも君の味方。分からないことは何でも先生に聞いて。」である。
いつもフシギダネが姿を消していく講師スペースなるものを意を決して覗いてみると、驚きの光景が広がっていた。
ロッカールームで指名が入るのを待つキャバ嬢のように、全員が携帯電話をガン見していたのである。
こんな中質問しに行ったら非難囂囂、よくて舌打ちの嵐だと思った私は踵を返して室長の元へと向かった。決して告げ口をしに行ったのではなく、分からないところがあるが講師スペースに非常に行きづらいので呼び出してほしい旨を伝達しに行ったのである。
その際に室長に言われた言葉を、何年も経った今も忘れたことはない。
「今は先生たちの休憩の時間だし、それにこんな問題は普通に考えればすぐに解けるんじゃないかな。わざわざ先生を呼び出すまでもないと思うけど。あ、あと僕は忙しくて教えてあげられないから。よろしく。」
逆転裁判第一話の矛盾点の指摘すら難しく感じてしまうほど国語力がなかった当時の私が、一秒もかからずに矛盾点を発見したのは後にも先にもこの時しかない。大人はよく嘘を吐く-そんなことは疾うの昔に理解出来ていたつもりだったが、いざ自分が信頼を(少しは)置いていた人間からやられると、多感な時期の少年は流石にこたえた。
それ以降少しの間、私は大人をそこまで信用出来ず、常に穿った見方をしてしまう期間が続いた。しかしその後、今でも恩師と仰ぐ人と出会うことになるが、これはまた別の機会に執筆するとしよう。
ここまでで、大言壮語を通り越しもはや虚言となり下がった標語が、多感な思春期にどのような影響を与えたか分かっていただけたことと思う。すぐに「調子乗ってんなぁ。」と割り切れたり見透かしたり出来ればいいが、対人経験値の少ない子ども達にとって、堅牢で巨大な盾の裏に隠されている雑兵を見つけ出すのは至難の業なのである。

標語とはまさに一本筋が通っているものだ。
それがぶれると先述したような虚言や世迷言といったものへと変貌を遂げる。目標到達のために遠回りをすることもあるだろうが、自らが掲げた標語に違わぬよう、初志貫徹し続けることが何よりも重要なのだと私は考える。
これからもずっと先生が生徒の、そして生徒が先生のポテンシャルを引き出せるような授業をするにはどうすればいいのか-思案を巡らせなければならないことはまだ当分尽きそうにない。
